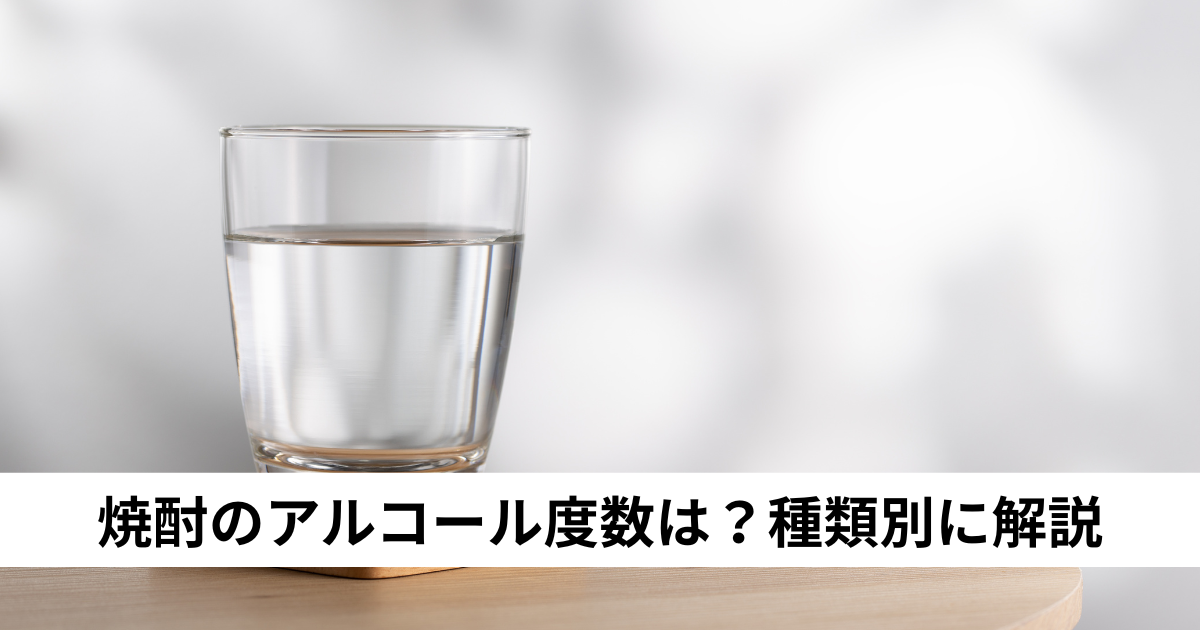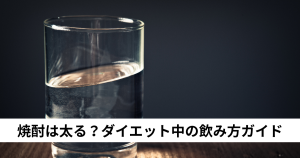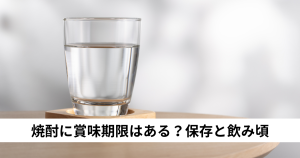「焼酎って、どのくらいアルコール強いの?」
ビールやワインに比べて度数が高いイメージがある焼酎。でも実際には、種類によってかなりの幅があることをご存知でしょうか?
この記事では、焼酎のアルコール度数の基本情報から、種類別の違い、飲み方ごとのおすすめ度数や注意点までを、わかりやすくご紹介します。
焼酎のアルコール度数は?基本は20〜25%
日本で一般的に流通している焼酎のアルコール度数は、20度〜25度が主流です。
特に本格焼酎(いわゆる乙類焼酎)は25度がスタンダード。
これは、日本の法律上の酒税区分や、水割り・お湯割りにしたときのちょうどよいバランスを基準にした設定です。
焼酎の種類と度数の違い
焼酎は大きく分けて「甲類(連続式蒸留)」と「乙類(単式蒸留)」の2種類があり、製法とともにアルコール度数にも違いがあります。
| 種類 | 製法 | 主な特徴 | アルコール度数の目安 |
|---|---|---|---|
| 焼酎甲類 | 連続式蒸留 | クセがなくクリア | 約20〜25%(一部35%) |
| 焼酎乙類(本格焼酎) | 単式蒸留 | 原料の風味が豊か | 約25%(一部30〜40%も) |
高アルコール焼酎も存在する?
高アルコールな焼酎も存在します。
通常の25度を超える「高アルコール焼酎」を好む方も少なくありません。
35度焼酎
-
主に果実酒づくりやリキュール用に利用
-
酒感が強く、少量で満足感がある
40度以上の長期熟成古酒
-
一部の泡盛や黒糖焼酎などで見られる
-
長期熟成による重厚な香りと飲みごたえが魅力
高アルコール焼酎はそのまま飲むよりも、水や炭酸で割って飲むのが一般的です。
飲み方別・おすすめアルコール度数の目安
どの焼酎を選ぶか悩んだとき、飲み方で考えてみるのも良いでしょう。
| 飲み方 | アルコール度数の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 水割り | 25度がちょうど良い | 割っても風味が残る |
| お湯割り | 20〜25度 | 熱で香りが立つため濃いめが◎ |
| ロック | 20〜25度 | 氷でゆっくり薄まる |
| ソーダ割り | 25度前後 | 炭酸の刺激と合う |
| ストレート | 20度以下が飲みやすい | 高度数はチェイサー必須 |
焼酎のアルコール度数と健康リスク
焼酎は蒸留酒であり、糖質・プリン体がゼロというメリットがありますが、度数が高いぶん飲みすぎには注意が必要です。
-
アルコール1gあたり:約7kcal
-
焼酎25度を180ml飲むと、アルコール摂取量は約36g(ビール約3本分に相当)
適量を守りつつ、割って楽しむのがポイントです。
焼酎の飲み過ぎラインはどれくらい?
焼酎は糖質ゼロ・プリン体ゼロといった健康イメージがありますが、アルコール度数が高いため、飲みすぎには要注意です。ここでは、健康的に楽しむための「適量」と「飲みすぎライン」の目安を見ていきましょう。
厚生労働省が定める「節度ある適度な飲酒量」
厚労省によると、1日平均純アルコール20g程度までが「節度ある飲酒量」とされています。
純アルコール量は次の式で計算されます:
飲料の量(ml) × アルコール度数(%) × 0.8 ÷ 100
この計算式に基づいて、25度の焼酎に換算すると──
| 焼酎の量 | 純アルコール量 | 飲酒の目安 |
|---|---|---|
| 約90ml(0.5合) | 約18g | 適量の範囲内 |
| 約180ml(1合) | 約36g | 飲みすぎ傾向 |
| 300ml以上 | 50g超 | 翌日に影響する恐れあり |
焼酎を健康的に楽しむためのポイント
-
1日1合(180ml)以内を目安にする
-
週に2日は「休肝日」を設ける
-
食事と一緒にゆっくり飲む
-
水割り・お湯割り・ソーダ割りなどで薄めて楽しむ
焼酎は“少量でも満足感がある”お酒なので、飲み方を工夫することで自然と摂取量をコントロールできます。
まとめ
焼酎のアルコール度数は、種類や飲み方に応じて選ぶのがコツです。
-
一般的な度数は20〜25度
-
甲類はクセがなくチューハイに最適、乙類は風味重視で25度が主流
-
高アルコール焼酎も一部存在し、アレンジに◎
-
割り方や体調に応じて度数を意識することが大切
風味や飲みやすさの好みに応じて、アルコール度数も選ぶ時代です。
上手に調整して、自分にぴったりの焼酎ライフを楽しみましょう!